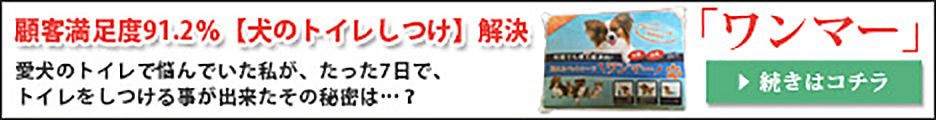【ぽっちゃり犬は危険がいっぱい?】犬のボディコンディションを知って健康長寿を目指そう!
- えふ子
- 2024年10月8日
- 読了時間: 6分

愛犬と過ごす時間は、私たちにとってかけがえのないものです。
そして、愛犬にはいつまでも元気でいてほしいと願うのは、飼い主として当然のことでしょう。
しかし、近年、犬の肥満は深刻化しており、様々な病気のリスクを高める要因となっています。
この記事では、犬のボディコンディションを正しく評価する方法、肥満のリスクと健康への影響、そして理想的なボディコンディションを維持するための管理方法について解説します。
愛犬の健康寿命を延ばし、共に過ごす時間を長く、そして豊かなものにするために、ぜひ最後までお読みください。
目次
犬の体型チェック:ボディコンディションスコア(BCS)を知ろう!
BCSとは?:肥満度を測る物差し
BCSの判定方法:見て触って評価
理想的なBCS:目指すべき体型
肥満のリスク:ぽっちゃり犬は要注意!
肥満になりやすい犬種:遺伝と生活習慣
肥満が引き起こす病気:様々な疾患のリスク
寿命への影響:健康寿命を縮めることも
ボディコンディション管理:食事と運動、そして定期的なチェック
食事管理:適切なフード選びと量
運動:年齢と体力に合わせた運動を
体重測定:日々の変化を見逃さないで
まとめ:理想的なボディコンディションで、愛犬と健康長寿!
犬の体型チェック:ボディコンディションスコア(BCS)を知ろう!
BCSとは?:肥満度を測る物差し
ボディコンディションスコア(BCS)とは、犬の肥満度を評価するための指標です。BCSは、主に5段階または9段階で評価され、肋骨の触りやすさ、ウエストのくびれ、お腹のたるみ具合などを総合的に見て判断します。
BCSの判定方法:見て触って評価
BCSの判定方法は、以下の通りです。
肋骨を触る:肋骨を軽く触ってみてください。
肋骨が簡単に触れる → 痩せすぎ
肋骨を触るのに少し力が必要 → 理想的
肋骨が全く触れない → 肥満
上から見てウエストのくびれを確認する:** 犬を上から見て、ウエストがくびれているか確認しましょう。
くびれがない → 肥満
横から見てお腹のたるみ具合を確認する:** 犬を横から見て、お腹がたるんでいないか確認しましょう。
お腹がたるんでいる → 肥満
理想的なBCS:目指すべき体型
犬種や年齢によって理想的なBCSは異なりますが、一般的にはBCS5段階評価で3、9段階評価で4~5が理想とされます。
BCS 5段階評価
1:痩せすぎ
2:やや痩せ気味
3:理想的
4:やや太り気味
5:肥満
BCS 9段階評価
1:痩せすぎ
2:非常に痩せ気味
3:痩せ気味
4:理想的
5:理想的
6:太り気味
7:肥満
8:非常に肥満
9:極端に肥満
肥満のリスク:ぽっちゃり犬は要注意!
肥満になりやすい犬種:遺伝と生活習慣
犬種によっては、遺伝的に肥満になりやすい傾向があります。
ラブラドール・レトリバー
ビーグル
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
ダックスフンド
パグ
フレンチ・ブルドッグ
これらの犬種を飼っている場合は、特に食事管理や運動に気を配り、肥満予防に努めましょう。
肥満が引き起こす病気:様々な疾患のリスク
肥満は、様々な病気のリスクを高めます。
糖尿病:
インスリンの分泌不足や働きが悪くなることで、血糖値が高くなる病気。
症状:多飲多尿、食欲増加、体重減少、白内障など。
心臓病:
心臓に負担がかかり、心臓の機能が低下する病気。
症状:咳、呼吸困難、運動不耐性、失神など。
関節疾患:
関節に過度な負担がかかり、炎症や変形が起こる病気。
症状:跛行(びっこ)、痛み、運動を嫌がるなど。
呼吸器疾患:
気管虚脱、気管支炎、肺炎など、呼吸器系の病気を悪化させる可能性があります。
症状:咳、呼吸困難、いびきなど。
皮膚病:
皮膚のひだに湿疹や炎症が起こりやすくなります。
症状:かゆみ、赤み、脱毛など。
その他:
肝臓病、膀胱炎、腫瘍など、様々な病気を引き起こす可能性があります。
寿命への影響:健康寿命を縮めることも
肥満は、犬の寿命を縮める可能性があります。ある研究によると、理想体重と比べて10% 肥満 な犬は、平均寿命が約1.8年短いという結果が出ています。
肥満は、様々な病気のリスクを高めるだけでなく、生活の質(QOL)を低下させることにも繋がります。愛犬と長く、そして健康に過ごすためにも、肥満予防は非常に重要です。
ボディコンディション管理:食事と運動、そして定期的なチェック
愛犬の体型を適切に管理することは、健康寿命を延ばす上で非常に重要です。肥満を予防し、理想的なボディコンディションを維持するために、以下の3つのポイントを心がけましょう。
食事管理:適切なフード選びと量
フード選び:
愛犬の年齢、犬種、活動量、健康状態に合わせたフードを選びましょう。
高品質なフードは、消化吸収が良く、必要な栄養素を効率的に摂取することができます。
肥満気味の犬には、低カロリー・低脂肪のフードを選びましょう。
アレルギーがある場合は、アレルゲンとなる食材を除去したフードを選びましょう。
食事量:
フードのパッケージに記載されている給与量を目安に、愛犬の体重や活動量に合わせて調整しましょう。
成犬は、1日2回に分けて食事を与えるのが一般的です。
子犬は、1日3~4回に分けて食事を与えましょう。
老犬は、消化機能が低下している場合があるため、少量ずつ、回数を分けて与えるのが良いでしょう。
食事回数:
1日に与える食事の回数は、犬の年齢や生活スタイルに合わせて調整しましょう。
食事を複数回に分けることで、血糖値の急上昇を抑え、肥満予防に繋がります。
おやつの与え方:
おやつは、主食のドッグフードの10%以内を目安に与えましょう。
与えすぎると、カロリーオーバーになり、肥満の原因となります。
低カロリーのおやつや、歯磨き効果のあるおやつを選びましょう。
運動:年齢と体力に合わせた運動を
適度な運動は、肥満予防だけでなく、ストレス解消や健康維持にも役立ちます。
運動量:
犬種や年齢、体力に合わせて、適切な運動量を確保しましょう。
運動不足は、肥満だけでなく、筋力低下や体力低下にも繋がります。
運動のしすぎは、関節や筋肉を痛める可能性があるので、注意が必要です。
運動の種類:
散歩、ドッグランでの自由運動、ボール遊び、フリスビー、アジリティなど、様々な運動があります。
愛犬が楽しめる運動を見つけ、飽きないように工夫しましょう。
注意点:
暑い時期や寒い時期は、熱中症や低体温症に注意し、散歩の時間帯や場所を工夫しましょう。
病気やケガをしている場合は、獣医師に相談してから運動を行いましょう。
体重測定:日々の変化を見逃さないで
定期的な体重測定は、ボディコンディション管理に欠かせません。体重の変化を把握することで、肥満の早期発見や、健康状態の変化に気づくことができます。
測定頻度:
少なくとも月に1回は体重を測定しましょう。
子犬や老犬、ダイエット中の犬は、より頻繁に測定する必要があります。
体重記録:
測定した体重は、記録しておきましょう。
体重の変化をグラフ化することで、より分かりやすくなります。
体重の変化に気づいたら:
体重が急に増えたり減ったりした場合は、病気の可能性もあります。早めに獣医師に相談しましょう。
まとめ:理想的なBCSで、愛犬と健康長寿!
愛犬のボディコンディションを適切に管理することは、健康寿命を延ばし、QOLを高めるために非常に重要です。
BCSを参考に、愛犬の体型を定期的にチェックし、肥満のサインに気づいたら、早めに対応しましょう。
食事管理、運動、体重測定など、日々の積み重ねが、愛犬の健康維持に繋がります。
愛犬と長く、そして健康に過ごすために、理想的なボディコンディションを目指しましょう。